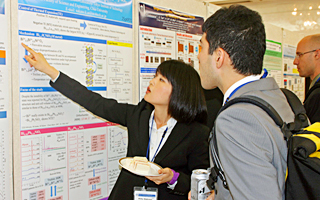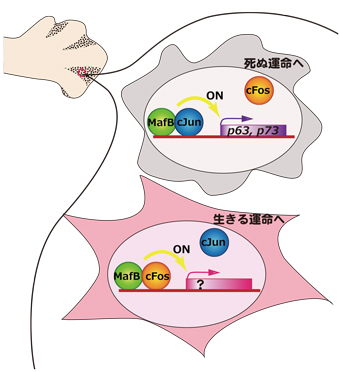学術研究懇談会(RU11)は、日本における最先端の研究・人材育成を担う、国立・私立という設置形態を超えたコンソーシアムです。北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の11大学で構成されています。
このたび、RU11の総長・塾長・学長は、大学における学術研究資源を活用した基盤の戦略的強化について声明をまとめました。
平成26年7月4日
大学における学術研究資源を活用した基盤の戦略的強化について(RU11緊急声明)
学術研究懇談会(RU11)
北海道大学総長 |
山口 佳三 |
東北大学総長 |
里見 進 |
筑波大学学長 |
永田 恭介 |
東京大学総長 |
濱田 純一 |
早稲田大学総長 |
鎌田 薫 |
慶應義塾長 |
清家 篤 |
東京工業大学学長 |
三島 良直 |
名古屋大学総長 |
濵口 道成 |
京都大学総長 |
松本 紘 |
大阪大学総長 |
平野 俊夫 |
九州大学総長 |
有川 節夫 |
学術研究懇談会(RU11)は、学術の発展を目的とし、研究及びこれを通じた高度な人材の育成に重点を置く、国立・私立という設置形態を超えたコンソーシアムとして、我が国全体の統合的な大学研究力強化に向けて連携して継続的な活動を行っています。
20世紀後半に我が国は、工業生産技術の革新を牽引力として世界トップレベルの経済大国となりました。しかし、現在、その経済成長モデルは成熟し、またアジア諸国が急伸する中、世界的な競争が熾烈になっており、世界における経済的地位を維持することは容易ではありません。
資源の乏しい我が国が今後も成長を続けていくには、人的資源による新しい知識を活用して新しい経済的価値を自ら生み出し続けなければなりません。そのためには、様々な分野でイノベーションを駆動することが不可欠であり、その基盤となる科学技術力の強化は喫緊の最重要課題です。
これまでの経済成長の過程で、大学、企業、公的研究機関に科学技術研究開発の基礎基盤が着実に蓄積されてきました。事実、これら長年かけて培ってきた知的基盤的資源こそが我が国の優位性であり、今後世界的競争を勝ち抜くための原動力となることは論をまちません。
大学や研究機関においても、4期に及ぶ科学技術基本計画のもとで、科学技術振興投資が行われ、競争的な研究資金が投入されています。一方、我が国の財務構造改革も重要な課題となる中で、大学や公的研究機関についてもより効率的かつ機動的な組織への転換が必要となり、国立大学の法人化や公的研究機関の独立行政法人化が行われ、既に10年あまり経過しました。その間、継続的に必要な組織運営に関わる基盤的財源の不安定化が進む中で、短期的な重点プロジェクトは促進するという状況が常態化し、その結果、組織基盤が大きく弱体化しました。特に、次世代を支える若手研究人材の育成や雇用の劣化をまねいていることは深刻です。
国立大学法人は、平成28年度から第3期中期計画期間に入ります。この期に研究力強化のための資金投入のあり方を抜本的に見直し、国民による投資が長期的な基盤強化に効果的に資するものとなるよう、戦略を立て直し、それを着実に進めて行く必要があります。特に、来年度は第2期中期計画を仕上げる最終年度として極めて重要な時期です。
このような大学を取り巻く状況を鑑み、学術研究懇談会(RU11)として、国立・私立という設置形態を問わず大学における学術研究の継続が、今後の我が国の発展にとって極めて重要であることを改めて発信します。特に留意すべきこととして、以下の2項目について提言します。
(1) 国立大学の基盤財源としての運営費交付金の配分見直しについて
国立大学の特別経費プロジェクトである「教育研究プロジェクト」は、中長期的な視点で地道な活動を支援することにより、大きな成果をあげるものが少なくありません。このようなプロジェクトは、優秀な若手人材育成のための土壌になるものでもあり、一定期間の継続性を確保することが重要です。このような観点から、教育研究プロジェクトの第3期中期計画以降の連続性について柔軟な対応を強く求めます。
世界水準の研究大学が学術研究の進展や社会構造の変化を踏まえた教育研究組織の柔軟な再編成・強化などの「機能強化」を図ることが極めて重要であることは論をまちませんが、その機能強化は、大学自身が自らの構想力と長期的視野に基づいてさらにその先の改革につながる萌芽を育むことと同時に行われなければなりません。
教育研究プロジェクトは大学における新しい教育研究活動の取り組みを支援するもので、現場からの提案をもとに各大学が厳選して提案しているものです。既存の部局の枠を越えた分野横断的な教育研究の展開や国立大学をハブとして私立大学とも連携し、国立・私立の枠を越えた教育研究の展開といった機能強化や大学改革の芽となる取り組みが数多く行われています。我が国の大学の機能強化は、国立・私立という設置形態を問わず大学の共通する喫緊の課題です。
以上のように、各大学における教育研究プロジェクトは、まさに第3期における大学の機能強化を先取りするものも多く含まれていますので、一律に中断に追い込むことは、大学改革を後退させてしまうことになりかねないと危惧します。
(2)大学院充実のための国公私立大学を通じた公募型事業について
大学院教育強化のためのG-COEプログラムや博士課程教育リーディングプログラム、グローバル化促進のためのG30プログラムなど、いずれも大きな成果をあげてきており、多くの事業が公募による時限事業として進められてきました。これら事業は最終年度まで継続することはもちろん今後の大学における国際化、機能強化などの観点から極めて重要なものであるため、今後も複数年にわたり継続する事業に対する国の恒久的な財政的支援を強く求めます。
従来、プログラム終了後の恒久化は、提案した大学の自己責任で行うこととされています。しかし、大学においては、間接経費や運営費交付金など共通経費財源は依然限られており、これらを恒久化することは財源的に極めて困難です。他方で、政府の科学技術・学術審議会や総合科学技術・イノベーション会議、産業競争力会議などは、こぞって我が国が世界で先頭を競っている分野などを軸にした卓越した大学院の形成に大きな期待を寄せています。第3期における運営費交付金の配分見直しにおいては、これら事業の成果を十分に評価し、これらの事業を通じて培われた資源を最大限に活用する観点から、学内資源の再配分の仕組みと相まってこれらの取り組みを重点支援する仕組みを構築すべきです。
お問い合わせ先
研究推進部研究企画課研究企画グループ
電話 03-5734-3803
E-mail pro.sien@jim.titech.ac.jp