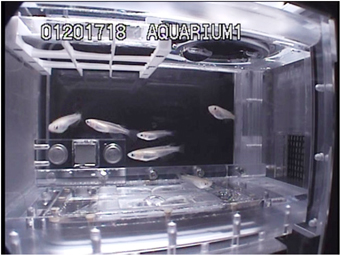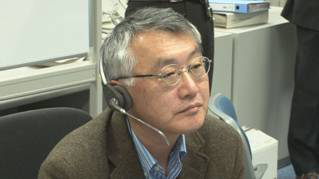要点
- 植物の光合成と同様、2段階のエネルギー移動で光を捕集
- 単位面積当たりの光量が少ない太陽光を安価な有機分子で集光し、人工光合成の反応中心へ効率よく光エネルギーを集約
- 高価で稀少な人工光合成用の光触媒の使用量を大幅に減らせる
概要
東京工業大学理工学研究科の石谷治教授と豊田中央研究所の稲垣伸二シニアフェローの共同研究チームは、2段階のエネルギー移動で、光を効率よく捕集する分子システムを初めて開発した。これは太陽エネルギーを高効率で化学エネルギーに変換する植物の光合成に匹敵する人工光合成の実現につながる成果だ。
光を吸収する有機分子を多量に、しかも規則正しく配置した壁で構成される多孔質材料のメソポーラス有機シリカ(PMO、用語1)に金属錯体を導入することにより、400個を超える有機分子が吸収した光エネルギーを、まず5つの金属錯体が集め、最終的に一つの分子に集約することができた。
この光捕集システムを、二酸化炭素の還元資源化や水からの水素発生を駆動する光触媒(用語2)と融合することで、人工光合成系の開発につながる。地球温暖化と化石資源の枯渇の緩和に役立つと期待される。
この成果は英国化学会の機関誌「Chemistryworld」で10月に紹介され、「Chemical Sciences」に2014年に掲載される。
研究成果
植物の光合成の光アンテナ系(用語3)と同様に、2段階で光を捕集・集約する人工的なシステムを世界に先駆けて開発した。この新たな分子システムを用いると、400個を超える有機分子が吸収した光エネルギーを、まず5つの金属錯体が集め、最終的に一つの分子に集約することが可能である。
![]()
図 |
(左) |
今回開発した光捕集・集約システム: 多くの有機基(ビフェリル)が導入された壁で構成された多孔質材料に、直鎖状の5核レニウム錯体の中心にルテニウム錯体が結合した分子が固定されている。 |
(右) |
このシステムは、400個を越える有機分子が吸収した光エネルギーを、まず5つのレニウム錯体が集め、最終的に一つのルテニウム錯体に集約することができる。 |
背景
地球温暖化と化石資源の枯渇への危惧が増し、再生可能エネルギー技術の新規開発が急務となっている。これらの問題を根本的に解決する夢の技術として、太陽光エネルギーを分子に蓄える技術、いわゆる人工光合成(太陽燃料)が注目されている。二酸化炭素を還元し燃料や化学原料を作る、また水から燃料となる水素を製造する光触媒の研究は近年、長足の進歩を遂げている。
しかし太陽光の密度が大変低いため、従来の光触媒では、それらを多量に使用しなければならないことになる。高価で稀少な金属を必要とし、さらに合成にも手間のかかる光触媒をこのような方法で使用することは実質的ではない。
一方、植物の光合成は、比較的単純な分子(クロロフィル等)の集合体(光アンテナ、LH2 と呼ばれる)を、葉の表面に幅広く配置することで、大面積で太陽光を捕集している。これをエネルギー移動により、まず単位面積当たり数の少ない LH1(やはりクロロフィルの集合体)に集め、その後、その近傍に配置された、構造が複雑な反応中心(用語4)へと移動させる2段階での光エネルギー集約ステムを構築することで、太陽光の効率の良い利用を達成している。
これまで、植物を真似た光捕集システムの研究は行われてきたが、多量の単純な有機分子から2段階で光を集約するシステムの報告はなかった。
研究の経緯
本成果は、東工大と豊田中研の2つの研究室が独自に開発してきたシステムを組み合わせることで得られた。
豊田中研の稲垣グループは光アンテナ「LH2」モデルとしてのメソポーラス有機シリカ(PMO)を世界に先駆けて開発した。稲垣シニアフェローらが開発したPMOは、光を吸収する有機分子を多量に、しかも規則正しく配置した壁で構成される多孔質材料である。
一方、東工大の石谷研究室は、LH1と反応中心のモデルとしての多核金属錯体(Ru-Re5)を開発することに成功した。5つのレニウム錯体が吸った光が、同じ分子内の中心に配置された一つのルテニウム錯体に集約される1段階光捕集系である。
今回、Ru-Re5をPMOの空孔に導入・固定した。この複合系は、光合成と同様に2段階で光エネルギーを集約することができる。すなわち、400個を超えるPMOの有機分子(植物のLH2に対応)が捕集した光エネルギーは、まずRu-Re5の5つのレニウム(LH1に対応)錯体が集め、最終的に、ただ一つのルテニウム錯体(反応中心に対応)に集約される。
今後の展開
今回開発した光捕集システムを、二酸化炭素の還元資源化や水からの水素発生を駆動する光触媒と融合することで、太陽エネルギーを効率よく吸収し、化学エネルギーに変換する人工光合成系の開発につながる。また、このシステムの導入により、高価で稀少な人工光合成用の光触媒の使用量を激減させることができる
用語説明
- 1
- メソポーラス有機シリカ(PMO): 様々な分子が入ることのできる"トンネル"が大量に、しかも規則的に並んだ多孔性の固体で、トンネルの壁が有機分子を多量に含んでいるので、光を効率的に吸収することができる。
- 2
- 光触媒: 光を吸収すると化学反応を引き起こす触媒
- 3
- アンテナ: 光合成において、光を吸収するLH2と呼ばれるクロロフィルの集合体
- 4
- 光合成の反応中心: LH2が吸収した太陽エネルギーを最終的に受け、酸化還元反応を開始する部分を反応中心と呼ぶ
論文情報
題 名 |
Efficient light harvesting via sequential two-step energy accumulation using a Ru-Re5 multinuclear complex incorporated into periodic mesoporous organosilica |
著 者 |
Youhei Yamamoto, Hiroyuki Takeda, Tatsuto Yui, Yutaro Ueda,ab Kazuhide Koike, Shinji Inagaki and Osamu Ishitani |
掲載誌 |
Chem. Sci., 2014, 5, 639-648
DOI: 10.1039/C3SC51959G![outer]()
Received 14 Jul 2013, Accepted 15 Oct 2013, First published online 16 Oct 2013 |
 骨の細胞が蛍光で光って見えるメダカ。赤は骨を作る細胞、緑は骨を吸収する細胞
骨の細胞が蛍光で光って見えるメダカ。赤は骨を作る細胞、緑は骨を吸収する細胞![]()
![]()